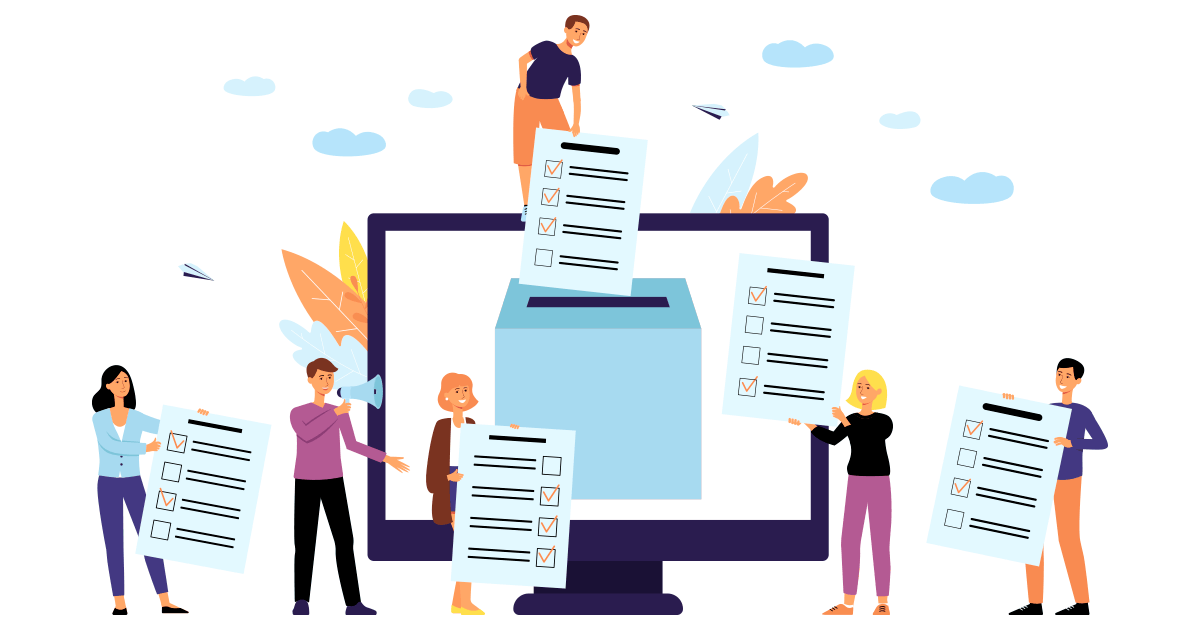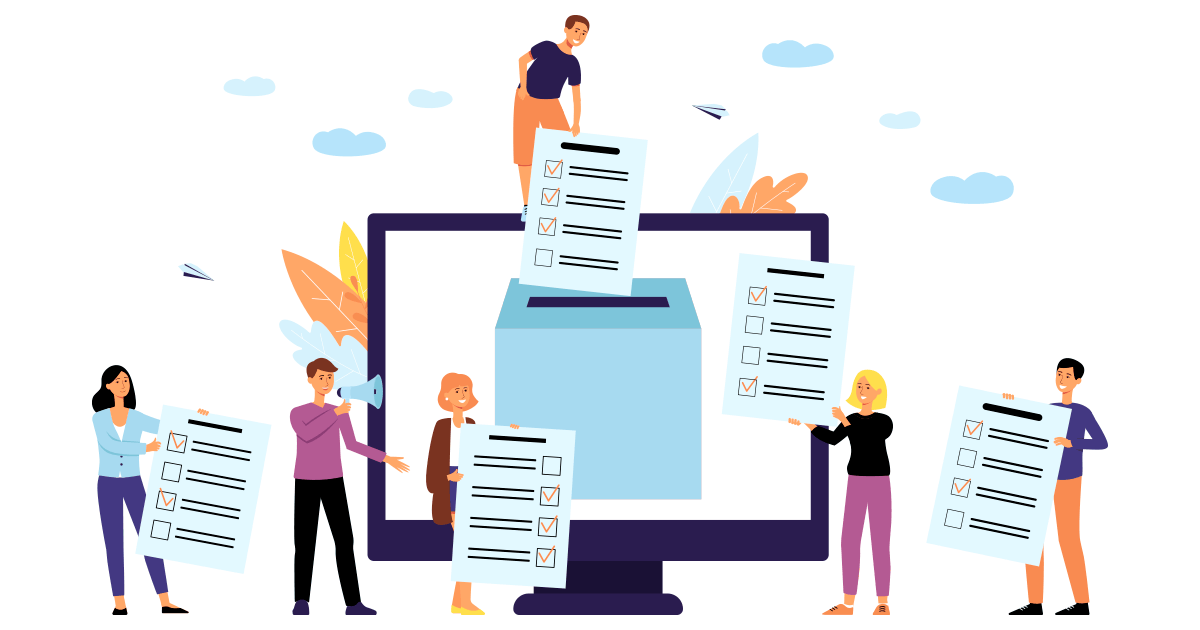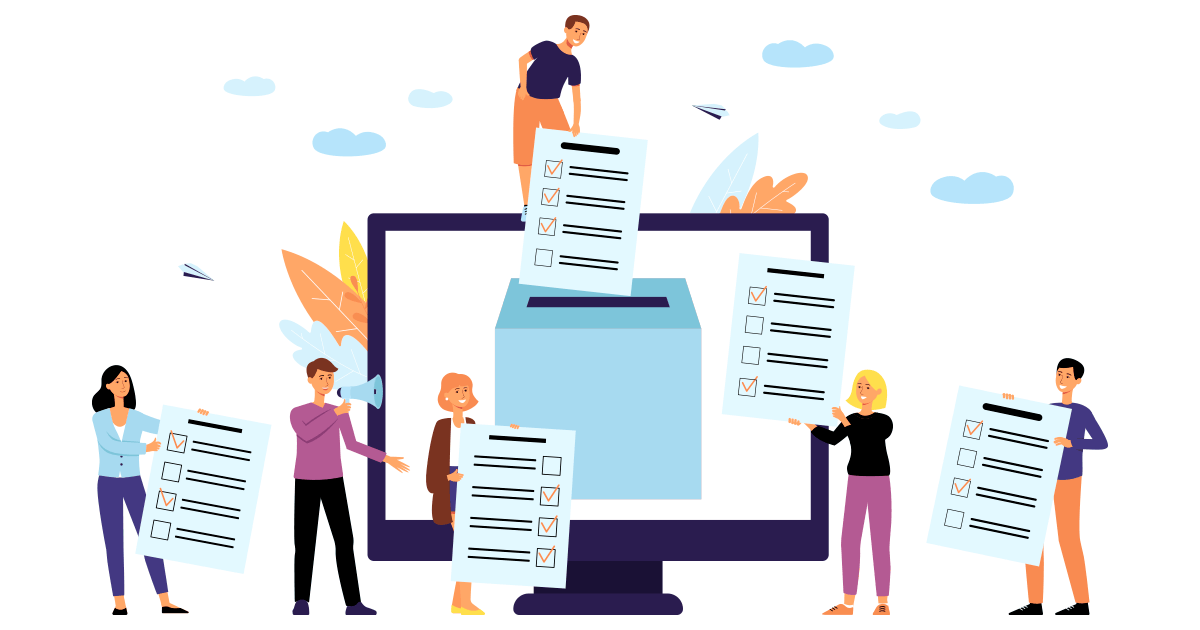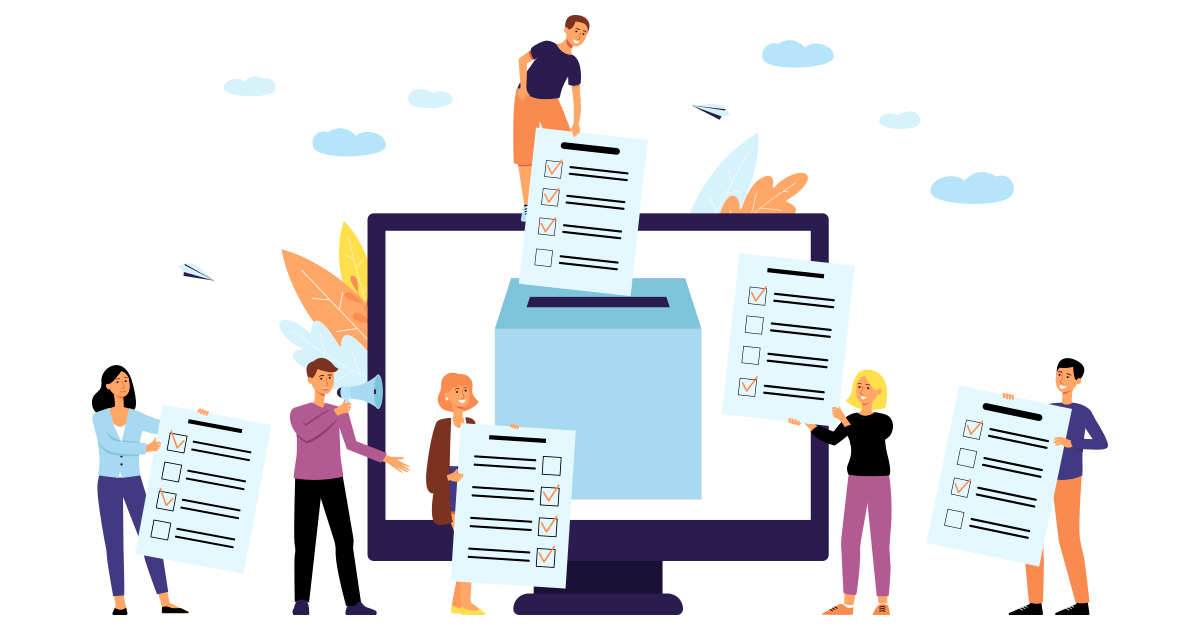「復興が完了している」と感じている人は54.7%
この度の調査は2021年2月19日から2月25日まで、震災時および現在も岩手・宮城・福島の被災3県に住む20歳から69歳の男女600人を対象に、インターネットを通じたアンケート形式で行われました。
まずは復興全体の進捗に対する被災した方々の評価です。
「東日本大震災から10年を迎え復興はどの程度進んでいると思いますか」の問いに対して、54.7%の人たちが「復興が完了している」と感じていると回答しました。一方で、およそ半数は「まだ復興が進んでいない」と感じているようです。県別にみると、宮城県が「復興が完了している」と感じている人の割合が64.5%と最も高く、岩手県が48.5%と最も低い結果となりました。
東日本大震災から10年を迎え復興はどの程度進んでいると思いますか?

県別の割合
| 地域 | 全体 | 完全に完了している | ほぼ完了している | あまり進んでいない | 進んでいない |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩手県 | 200人 | 4.0% | 44.5% | 48.5% | 3.0% |
| 宮城県 | 200人 | 7.0% | 57.5% | 34.5% | 1.0% |
| 福島県 | 200人 | 7.5% | 43.5% | 43.5% | 5.5% |
今、必要だと思う社会インフラで最も回答が多かったのは「防災インフラ」
それでは、どんな分野で復興が実感でき、どんな分野で実感できていないのでしょうか。復興を実感できているものとしては、「道路や鉄道、橋、堤防などインフラ(86%)」が最も多く、「病院/学校/役所などの公共施設(85.5%)」が続きました。一方で、「景気や雇用など地域経済活動 」については 46.8 %と、復興を実感している人は半数以下に留まっています。インフラなどのハード面では復興が進んでいることを実感しているものの、経済活動においては復興を実感できていない方が今も多くいる実態が明らかになりました。
以下のそれぞれの項目について、あなたは東日本大震災以降復興したという実感がありますか?

県別の割合
| 地域 | 全体 | 実感している | やや実感している | あまり実感していない | 実感していない |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩手県 | 200人 | 20.5% | 32.5% | 39.0% | 8.0% |
| 宮城県 | 200人 | 31.5% | 45.0% | 21.0% | 2.5% |
| 福島県 | 200人 | 37.5% | 36.0% | 17.0% | 9.5% |
| 地域 | 全体 | 実感している | やや実感している | あまり実感していない | 実感していない |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩手県 | 200人 | 13.0% | 19.5% | 45.5% | 22.0% |
| 宮城県 | 200人 | 17.5% | 35.0% | 39.0% | 8.5% |
| 福島県 | 200人 | 20.5% | 35.0% | 33.0% | 11.5% |
現在、各地で様々な復興まちづくりが進められていますが、いま被災地で求められる社会インフラについても質問してみました。
アンケートでは、半数近い44.7%が「災害を抑制する堤防や砂防ダムなどの防災インフラが必要だと思う」と回答し、防災インフラに対する期待が高いことがわかりました。また、上記と同程度の割合で「町を活性化させる観光インフラ(ホテルや観光施設等)」、「スマートなまちづくりにむけた情報通信インフラ」と回答しており、防災はもちろん、経済活性化やスマート社会への意識の高さもわかる結果となりました。
東日本大震災後、各地で様々な復興まちづくりが進められていますが、あなたが今、必要と思う社会インフラはなんですか?

半数以上が今後の復興事業に「地元民の雇用創出」や「過疎化対策」を期待
今後の復興事業において期待する施策について質問したところ、最も多かったのは「地元民の雇用創出(63.5%)」、次いで「高齢化、過疎対策(52.8%)」、「経済補償(44.3%)」となりました。
地方の課題となっている人口流出、高齢化、過疎化などへの対策は、被災地においても特に期待値が高いことがわかりました。
今後の東日本大震災からの復興事業において期待する施策はなんですか?

2人に1人が地区防災計画をまったく知らず、取り組みへの参加経験なし
東日本大震災での経験を踏まえ、行政による「公助」に加え、「自助」や「共助」といった考え方が取り入れられ、この自助・共助を推進するための地区防災計画※の策定が期待されています。今回のアンケートでは、この地区防災計画についても聞いてみたところ、「取り組みを行っている」との回答は21.2%に留まっており、「まったく知らず、取り組みに参加したこともない」の回答が半数を超え、「地区防災計画」の浸透度が低い実態がわかりました。
※ 地区防災計画とは、災害対策基本法に基づき、一定の地域に居住する住民どうしが、自分たちの地域の人命、財産を守るために助け合い(共助)行動するために策定する、自発的な防災活動に関する計画のこと
東日本大震災以降、「自助・公助・共助」という考え方のもと、市町村が策定する「地区防災計画」以外に、住民やコミュニティによる「地区防災計画」の策定が求められています。この「地区防災計画」についてお聞きします。ご自身の住むエリアでは、「地区防災計画」の取り組みを行っていますか?

地区防災計画「取り組みがない、知らない」 社会的関心の低さが理由か
ご自身の住むエリアでの地区防災計画の取り組みがない、または知らないと回答した人に理由を聞きました。
回答の多かった順に「行政の働きかけがない(46.9%)」、「専門知識がなくどのように策定していいかわからない(42.1%)」、「住民同士のつながりが希薄化し協力が得られない(35.5%)」、「マスコミでも報道されない(30.2%)」となりました。自治体の取組みにもばらつきがあることや、報道で目に触れる機会も少ないことなど、社会的な関心の低さや、普及に向けた課題があることがうかがえます。
東日本大震災前後で行った防災対策 多いのは「避難所とハザードマップの把握」
東日本大震災前後で、行なった防災対策について質問をしました。
震災前から行っていた対策で最も多かったのは、「避難所の把握(36.8%)」、次いで「ハザードマップの把握(27.5%)」でした。各項目とも震災をきっかけに対策する方が一気に増えていますが、中でも防災アプリの増加率は他項目の中で突出しており、この10年でのスマホの普及率向上が関係している可能性もあります。一方で、震災前後ともに「何も対策していない」という方が約3割いることがわかりました。
被災経験者であっても一定規模の方は、その後に特段の行動変容が起こるわけではないようです。
あなたが、東日本大震災前から行っている防災対策、東日本大震災後から行っている防災対策についてあてはまるものをそれぞれお答えください

まとめ
今回の調査では、東北3県に在住の東日本大震災経験者の、被災から10年経過しての復興現状や、今後の復興事業への期待などがわかりました。インフラに関しては、全体的に8割以上の方が復興を実感しているようです。一方で、景気や雇用など地域経済について復興を実感している方は、5割程度になりました。今後の復興事業において期待する施策についても、「地元民の雇用創出」、「過疎対策」、「経済補償」の割合が多く、引き続き経済面での復興施策が重要だという事がわかりました。
昨今、重要性が謳われている住民やコミュニティによる「地区防災計画」については、「まったく知らず、取り組みに参加したこともない」との回答が半数を超え、言葉自体の浸透度や社会的な関心が低いこと、また普及に向けた課題がある可能性も見えてきました。
本調査は、防災に関わる業務を主たる事業の一つとしている当社の今後のサービスの向上および、社会貢献の一環として実施しております。
応用地質では、今後も、インフラや自然環境、災害などに関する独自調査を行なって参ります。
詳しい調査結果については以下もご覧ください。
2021年3月9日 応用地質株式会社プレスリリース「東日本大震災経験者の復興に関する意識調査」