自然共生サイト / OECMトータル支援サービス

概要
国による自然共生サイトの認定制度とOECMの登録
2023年、30by30目標※1の達成に向け、環境省は「自然共生サイト」の認定制度を開始しました。自然共生サイトは、民間の取り組み等によって生物多様性の保全が図られていることを国が認定した区域です。2025年3月末現在、328か所 (合計面積9.3万ha) が認定されています。
自然共生サイトの認定区域のうち、保護地域 (国立公園等) との重複を除いた区域が、「OECM※2」として国際データベースに登録されます。
2025年4月には「地域生物多様性増進法」が施行され、これにより認定制度が法定化されました。自然共生サイトおよびOECMに係る取り組みの今後一層の促進が期待されます。
- 30by30目標
2030年までに陸域と海域のそれぞれ30%以上を保全する目標です。2022年12月に生物多様性条約COP15で採択された「昆明・モントリオール生物多様性枠組」の2030年グローバルターゲットとして設定されました。日本が定めた「生物多様性国家戦略」の行動目標にもなっています。 - OECM
Other Effective area-based Conservation Measures の略称で、私有林や里地里山など保護地域 (国立公園等) 以外であって生物多様性の保全に資する地域のことです。30by30目標の達成は、保護地域とOECMの面積を合わせて算定して評価されます。
自然共生サイトに該当する緑地の例
以下の条件を満たす区域が自然共生サイトに該当します。
- 生物多様性の価値を有し、
- 企業、団体・個人、自治体による様々な取り組みにより、
- (本来目的に関わらず、) 生物多様性の保全が図られている区域
これらに該当する緑地の例を示します。
企業の森、ナショナルトラスト、バードサンクチュアリ、ビオトープ、自然観察の森、里地里山、森林施業地、水源の森、社寺林、文化的・歴史的な価値を有する地域、企業敷地内の緑地、屋敷林、緑道、都市内の緑地、風致保全の樹林、都市内の公園、ゴルフ場、スキー場、研究機関の森林、環境教育に活用されている森林、防災・減災目的の森林、遊水池、河川敷、水源涵養や炭素固定・吸収目的の森林、建物の屋上、試験・訓練のための草原 など。






自然共生サイト / OECMの認定・登録による意義・メリット
1. 生物多様性の価値を国が証明
緑地のもつ生物多様性の価値が、国によって国際的な整合性をもって客観的に証明されます。
2. 30by30目標達成への寄与
企業として、生物多様性条約に基づく世界目標および我が国の生物多様性国家戦略の行動目標である30by30目標の達成に寄与します。
3. 顧客へのアピール
顧客に対して、生物多様性や自然との共生に配慮している企業であるとアピールできます。
4. 近隣住民へのアピール
近隣住民に対して、生物多様性や自然との共生に配慮している企業であるとアピールできるとともに、身近な緑地の機能や効用に目を向けてもらう契機にもなります。
5. 投資家へのアピール
投資家に対して、自社ホームページや環境報告書等を通じた情報開示によりアピールできます。さらに、企業の事業活動に起因する自然への負荷の低減等に関する分析や対策と関連づければ、TNFDの提言※3に則した情報開示にも活用が可能です。
- TNFDの提言
2023年9月に公表された自然関連財務情報開示タスクフォース (Taskforce on Nature-related Financial Disclosure, TNFD) の提言です。企業に対して自然に関連した事業リスク、事業機会等の情報開示を促すものです。
6. 地方公共団体へのアピール
地方公共団体は、生物多様性基本法に基づき生物多様性地域戦略の策定に努めることとされています。この戦略では、生物多様性の保全に様々な主体が関わることが重要なテーマであり、企業による自然共生サイトの取り組みは地方公共団体へのアピールとなります。
7. 生物多様性の保全活動の実証の場としての活用
自然共生サイトを技術の実証の場とすることで、企業の新たな事業機会の創出に寄与します。
8. 社内のネイチャーポジティブに関する理解の促進
自然共生サイトの認定により、緑地がもつ生物多様性の価値が明確になり、生物多様性や自然との共生の重要性など、ネイチャーポジティブに関する社内の理解が深まります。
9. 国による支援策
国 (環境省) は、自然共生サイトに対して次のような支援策を講じています。 (2025年度時点 最新の情報は環境省Webサイトをご覧ください)
- 生物多様性保全推進支援事業 (交付金) による、自然共生サイトにおける管理手法の改善などの取り組みに対する活動経費の補助
- 自然共生サイトの検索ナビ「生物多様性見える化システム」へのサイト情報、活動情報等の掲載
- 自然共生サイトとその支援者とのマッチング機会の提供や、支援者に対する支援証明書の発行
自然共生サイト / OECM トータル支援サービスの流れ
自然共生サイトに関する手続き・作業の流れは、以下の図のとおりです。
当社は、自然共生サイトの手続き・作業を行う企業等の皆さまを、「増進活動実施計画」の作成・申請から認定後の計画の実施に至るまで、トータルに支援します。
自然共生サイトに関する手続き・作業の流れ
- 地域生物多様性増進法に基づき作成して国に申請する計画の名称
- 申請の受付や予備審査等は、独立行政法人環境再生保全機構が担当
- 認定の審査期間は、6~7か月程度
- 計画の実施区域が「自然共生サイト」と呼称される
当社が行う支援
1.「増進活動実施計画」の作成・申請に対する支援
増進活動実施計画の作成に当たっては、生物や生態系に関する知見や技術が必要です。
当社は、長年培ってきた生態系調査などの実績と知見を基に、生物の専門知識をもつ社員が、同計画の作成を支援します。
このほか「社員さま等への勉強会の開催」など、例示した支援以外も対応しますので、ご相談ください。
2.「増進活動実施計画」の認定後の支援
増進活動実施計画の認定後、計画に記載した活動内容の実施と、その実施状況および効果の確認結果の報告が求められます。
当社は、認定された計画の実施とその効果の把握や評価についても支援します。
このほか「自然共生サイトを利用したイベントの提案・開催」など、例示した支援以外も対応しますので、ご相談ください。
当社の自然共生サイト / OECM

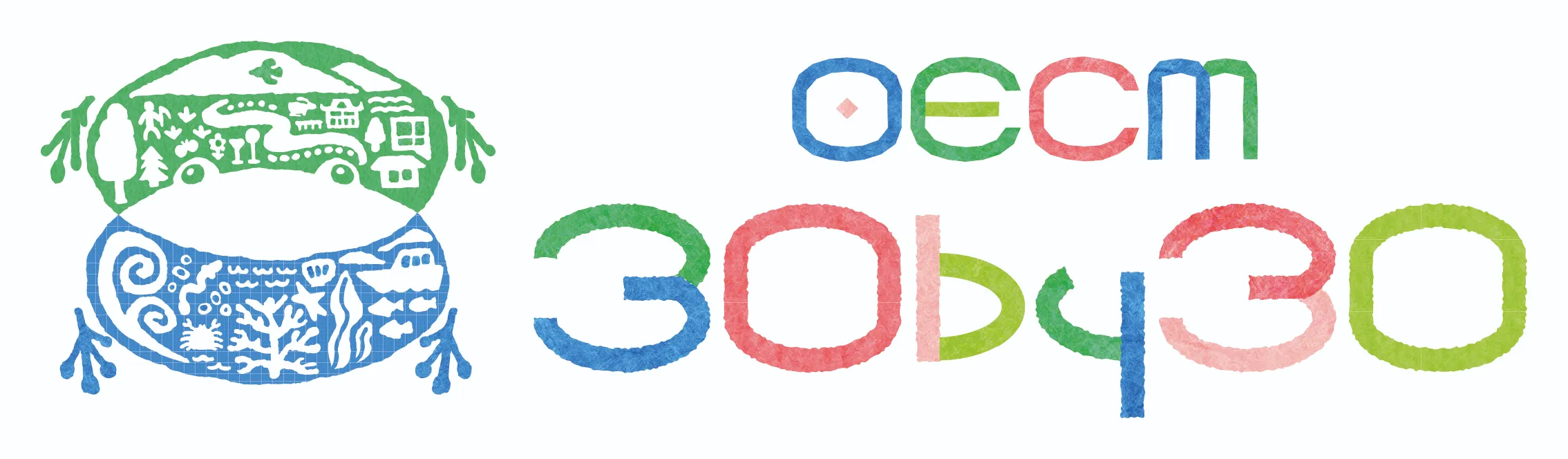
2024年3月に、当社つくばオフィス内の緑地が、自然共生サイトの認定を受けました。
また、2024年8月には、OECMに関する最も包括的な国際データベースである世界OECMデータベース (WD-OECM) に登録されました。


| 場所 | 茨城県つくば市 |
|---|---|
| 面積 | 2.4ha |
| 活動目的 | 地域住民や従業員への自然景観の提供、地域の生物多様性保全に貢献すること |
| 生物多様性の価値 |
生態系サービスを提供する健全な生態系緑地には、シラカシ、ケヤキ、コナラ、メタセコイアなどの高木が分布する樹林エリアと、主にイネ科草本群落が分布する草地エリアが併存し、そこに昆虫、爬虫類、ほ乳類、鳥類などの生物が加わり、自然景観を形成しています。 

希少種環境省や茨城県より希少な種として指定されている鳥類や植物が、複数種類確認されています。 

|
CONTACTお問い合わせ
- 電話でのお問い合わせ
- 029-851-6621
- 営業時間 9:00~17:00 (土日祝日除く)